誠実・公正・迅速 あなたの目線で紛争の適切な解決に努力します。
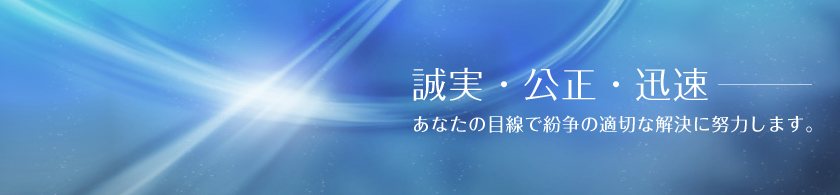
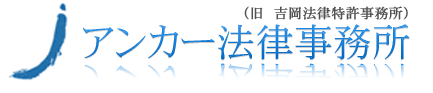
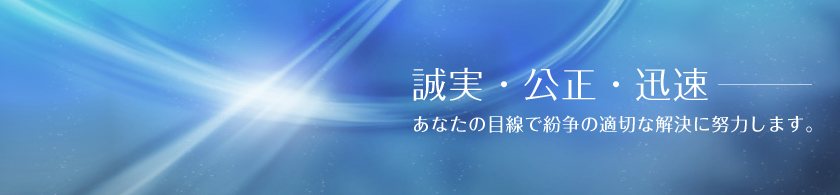
1 事案の概要
本件は、2棟の一戸建て住宅の新築工事の設計及び施工を一括して発注した者が、工事に瑕疵がある等と主張して、建築会社に対し、①工事の瑕疵について、請負契約上の瑕疵担保責任に基づく瑕疵修補に代わる損害賠償請求及び②被告が工事完成後のメンテナンスを行っていないことについて、メンテナンス合意違反の債務不履行に基づく損害賠償請求として、補修費用等及び遅延損害金の支払を求めた事案。
主たる争点は、①各種瑕疵の有無と損害額、②損害賠償請求権の期間制限、③慰謝料請求の可否についてである。
2 裁判所の判断
(1)各種瑕疵の有無について
ア 鉄柱の根がらみを切断した瑕疵について
根がらみを切断するに当たっては、施工者として、鉄柱の設置目的を考慮し、各鉄柱の固定性を確保すべく、その基礎構造計算の上、支柱の基礎形状や根入れ深さの検討を行うべきであった。それにもかかわらず、これらの検討をせず根がらみを切断したことにより、各鉄柱の固定度を低減させことは、契約上求められるべき水準に達しない施工をした瑕疵があるとした。なお、サービス工事であるとしても、施工水準に満たない施工は許容されるものではないとした。
イ 基礎前面の被り圧不足について
基礎全面においてかぶり厚が不足していた部分は、補修工事により補修され、補修部分の基礎の質及び耐力が低下していることを認めるに足りる的確はなく、一定期間、定期的な点検及び防水材の塗布が必要であることを示す的確な証拠はなく瑕疵ではないとした。
ウ 基礎のシース筋の過大な台直しを行った瑕疵について
台直しを行ったシース筋の一部に、鉄筋コンクリート造の配筋の指針として規定された傾斜の基準(日本建築学会の鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説)である6分の1を超える傾斜となったこと部分があり、構造耐力が正規のシース筋よりも劣る状態となっていることが認められることから、その部分については、一般的な施工水準として許容されず、あるべき施工内容に関する当事者の合理的意思に反し瑕疵に該当するとした。なお、注文者は、修復不能な瑕疵と主張したが、裁判所は修復可能とした。
エ ボイド(紙製の円筒)を残存した瑕疵について
ボイドの除去作業を行ったものであり、その多くが基礎の中に残っていることを認めることはできず、仮に一部残存していたとしても、残存しているボイドがどの程度あって、それがどのような状態となることにより基礎に影響を及ぼすかという機序が明らかとなっているものではなく、ボイド全てを取り除かない場合、ボイドが水分を吸ってしまい、近くの鉄筋に悪影響を及ぼすことになるとの原告の主張については採用できないとした。
オ 主要鉄筋を切断した瑕疵について
主要鉄筋を切断した事実は認められるが、他方、建築会社は、主要鉄筋の補強のため、当該箇所にステンレス板を張り、壁面全体にGRC板を張って、新たな壁板を設置したり、炭素繊維による補強工事を行ったりしたこと、その結果、補強後の本件1の建物は、構造計算上、問題がない状態となっていることが認められ、相当な補修がされているものと評価でき、瑕疵に当たらないとした。
カ 換気システムの瑕疵について
喚起ステムは、対象建物において、想定されていたどおりの空気の流れを発生させることは困難であったことから、当該換気システムの設置という設計自体に問題があり、設計瑕疵があったとした。なお、損害としては、設置費用のみ認め、注文者側が主張した他のシステムの設置費用までは認めなかった。
キ 塩ビ管や電気コードが貫通している基礎の内側に防錆塗料を塗布した瑕疵について
建物の外部北側の分電盤下の電気幹線のスリーブ及び外部西側の基礎電気幹線のスリーブに、防錆処理のためにタールエポキシを塗布したことが認められるが、通常、埋設配線はCD・PF蛇腹管に納めて埋設するため、揮発性トルエン(タールエポキシ)の影響はないことがうかがわれ、また、電気配線に揮発性トルエン(タールエポキシ)が直接塗布されたことを認めるに足りる的確な証拠はないから、施工が施工水準に劣るものであることを認めることはできないとした。
ク 給排水管の図面を作成していない瑕疵について
建築会社は、建物の設計及び施工を一括して請け負ったものであるから、完成後の給排水管の配管図を作成し、注文者に対して配管の状況が判明する資料を引き渡す債務を負っていると認められ、瑕疵に当たるとした。
(2)損害賠償請求の期間制限について
当事者間の交渉経緯において、建築会社の担当者が「鉄筋の切断および台直しの点について、基本的に当社側の落度により原告にご迷惑とご心配をおかけしていることから、「出来るだけのことを致します」と申し述べて、瑕疵に当たるかどうかに関わりなく、原告の要望、苦情に応えてきたものです。」と記載されているとおり、建築会社側として、誠意をもって対応したいとの努力目標を述べたものであり、直ちに何らかの合意をしたとは認められない余地があるものというべきであることから、これをもって注文者が期間内に権利保存行為を行ったとは言えないとした。
(3)慰謝料請求について
瑕疵の有無、程度、その他本件の一切の事情を考慮しても、本件において、注文者に金銭をもって慰謝すべき程度の精神的損害が生じたとは認められないとした。
3 コメント
瑕疵の判断について、技術的なものについては、的確な技術的な根拠が示されない限り、裁判所としても安易に瑕疵とは認めません。また、慰謝料については、通常、瑕疵が修補されれば足りるとし、認めない傾向にあります。また、権利保存行為は客観的に明確に行うことが必要です。
(2024.1.28)
1 事案の概要
本件は、内装工事の下請業者が元請業者の請け負った戸建住宅のリフォーム工事について、元請業者に対し、追加変更工事報酬を含む請負報酬の支払を求めたのに対し、元請業者が下請業者に対し、改正前民法の瑕疵担保責任に基づく修補に代わる損害賠償等を求めた事案である。
主たる争点は、①追加工事代金支払い合意の有無、②瑕疵の有無、③瑕疵担保責任保険の保険金との損益相殺についてである。
2 裁判所の判断
(1)追加工事代金支払い合意の有無について
住宅改修工事について、下請業者と元請業者で協議して、報酬額を400万円(税抜)として、その範囲で、見積書に記載されている工事内容を、間取りの変更を含めて、大幅に変更しており、その工事内容は当初の見積書記載のものから大きく異なっていたが、この変更によっては報酬額が変更されない認識で協議されていたことが認められる。
そうすると、下請契約締結時より前に施工することになっていた工事については、特段の合意がされているなどの事情がない限り、報酬400万円(税抜)に含むものとして請契約が締結されていたものと推認できる。
また、下請業者が追加工事であると主張するものについては、本工事に付帯する工事は当然に本工事の一部で追加工事に当たらず、当初の見積書に記載のない工事についても、上記のような契約の特殊性から、有償として追加の費用が発生する旨の説明がない以上、無償との合意が成立していたと推認できる。
(2)瑕疵の有無について
耐震補強については、耐震診断が前提となるところ、これが予定されていなかったことから、可能な範囲で行うという程度の合意であり、瑕疵に当たらないとした。また、クローゼットのサイズ違いについては、その他事実関係から図面に誤記があったものとして、図面と異なることが瑕疵に当たらないなとした。雨水の侵入については、漏水検査が予定されていないことなどから可能な範囲で行うという程度合意であり、また、漏水原因と下請業者の作業との因果関係が不明であるとして瑕疵に当たらないとした。厨房の防水処理は立ち上がり不足を瑕疵としたが、元請業者の請求額は認めず、瑕疵の内容に応じた相当な費用の限度とした。
(3)瑕疵担保保険の保険金との損益相殺について
保険金給付の前提となった保険事故の内容と下請業者の施工瑕疵の内容とは同一性を欠いているといえ、下請業者の施工瑕疵に基づいて保険金請求をした場合に保険金が支払われるか否か、保険金の支払によって、保険者が元請業者の下請業者に対する瑕疵担保責任に基づく修補に代わる損害賠償請求権について保険法25条1項による保険代位をするか否かは判然としないといわざるを得ないが、保険金請求の対象となる保険事故の内容は下請業者の瑕疵の内容とは異なるものの、同一の現象を対象として請求され、かつ、同請求において必要とされた工事は、元請業者が行なった工事や本件意見書で相当な補修方法と指摘されている工事の内容と重複する内容であるなど、下請業者の瑕疵によって生じた元請業者の損害と、保険金が前提とする被告の損害との共通性が認められ、元請業者が下請業者から賠償を受けた場合には、保険代位が生じないので、元請業者は保険金を保険会社に返金しない限り、保険金と併せて、共通性のある損害について、それぞれ金員を得ることで、二重の利益を得ることになる。以上の事実関係に照らすと、このような主張をすることで、元請業者が二重の利益を得ることは、信義則に反し許されないというべきである
3 コメント
本件は、当初見積書の内容から工事内容が大きく変更されたが、報酬額は当初額のとおりという合意の成立があったとの認定を前提としているため、追加工事の多くは、追加費用の説明がなかたから当初の報酬額に含まれるものとしました。また瑕疵の有無についても、合意違反の瑕疵については、当初の契約の内容で予定されていなかった工事であるとして瑕疵ではないとされました。つまり、当初の契約が大きく工事内容を変更しつつ、報酬額を変えないというものであったことが影響していると考えられます。追加工事の場合は、その都度議事録を残しておくのが望ましいと言えます。
(2024.1.6)
1 事案の概要
本件は、建築の企画・設計・工事監理を主たる業務とする有限会社が、組合員の取り扱う医療資材、医療機器等の共同購入、組合員のためにする共同施設の設置及び管理運営等を行う組合設計課管理を行う会社に対し、主位的に、設計監理契約が設計管理業者の責めに帰することができない事由によって終了したとして、改正前の民法648条3項に基づき、既にした履行の割合に応じた報酬と遅延損害金を、予備的に、商法512条に基づき、相当報酬及び遅延損害金を事案である。
主たる争点は、①設計管理契約の成否、②契約解除について設計管理業者側に帰責事由の有無、③出来高の評価である。
2 裁判所の判断
(1)設計管理契約の成否について
発注者側が依頼のメールをしているが、理事会を経た後に正式決定をする旨の記載があり、報酬の額や支払方法等について具体的な協議も行われていないことから、メールの時点では設計監理契約の成立はしていないとした。
一方で、両当事者の間で新築工事に関する打合せが繰り返し行われ、入居予定事業者や関係機関からのヒアリングなどを行われた上で、建物の平面図等を内容とする基本構想と題する書面が複数作成され、発注者に提出されていること、設計監理業者から発注者側代表者に建物に関する設計・監理業務についての注文書・請書案が提出され、発注者側の担当者から契約書を作成してほしいとの意向を受けて、設計管理業者が設計・工事監理業務の内容、同業務の期間、業務報酬の額、支払方法等について記載した注文書・請書の案を改めて作成し、発注者側の担当者ら送付していること、同注文書・請書の案の内容に対し、発注者側から何らかの異議が述べられていないこと、発注者側担当者から、契約がのびのびになっていて申し訳ないが、会議終了後だと落ち着かないので、改めたところできちんと落ち着いて契約したい旨のメールが送られていること、その後も、両当事者間で建物に関する打合せなどが行われていること等から、注文書・請書の内容により、建物についての設計監理契約が成立したものと推認することができるとした。
なお、建築を予定した土地が開発許可の必要な市街化調整区域であったことから、発注者側から、開発許可を受ける前に設計監理契約を締結することはないとの主張がなされたが、開発許可申請に当たっては、建築面積や延べ床面積を明記した予定建築物の平面図、立面図等の提出が求められていること等から、開発許可申請を行うためには、開発許可申請業務と設計業務とは並行して進めなければならないものであったとして、発注者側の主張を排斥した。
(2)契約解除について設計管理業者側に帰責事由があるかについて
発注者側が複数の設計管理業者の帰責性を主張したが、証拠上、主張の事実が認められないとした。
(3)出来高の評価について
まず、基本設計について、建築主との協議を行い、建築主の建築物に対する要求その他の諸条件を設計条件として整理し、法令上の諸条件やインフラ設備の状況等についての調査及び関係機関との打合せを経た上で、基本的な設計方針を策定し、同方針に基づいて設計図書を作成するとともに、概算工事費の検討や建築主への説明等を行う業務であると解されるとし、本件では、設計管理業者は、発注者や入居予定者と繰り返し打合せ等を行い、その要望等を聞き取った上で、各室リストや平面図等を内容とする基本構想と題する書面を複数作成し、その中で、各時点における被告や入居予定者の要望事項等を設計条件として整理しており、同基本構想の内容に関しては、打合せの中で、発注者側に説明、報告をしており、建築条件の調査等を行っているが、契約終了時点においても、建物の各室の配置や用途等については、未だ最終確定には至っておらず、引き続き、発注者らの要望等のヒアリングや図面の修正等が予定されており、設計管理業者が作成した基本構想においては、外装・内装の仕上げ、設備の性能目標及び仕様、耐震性能及び構造性能の目標や構造方法などについては盛り込まれておらず、立面図や断面図、工事費用についての概算見積書も添付されておらず、役所関係は一度訪問したにとどまり、建築確認申請の関係機関については、指定確認検査機関に一度架電し、一度訪問したにとどまる等として、設計管理業者の履行割合を基本設計業務の約40%とした。
その上で、一般的に、設計監理業務全体の中での設計業務の割合が80%、そのうち基本設計の割合が29%とされているとし、契約金の額×80%×29%×40%の計算で出来高を算出した。
3 コメント
設計管理契約や工事請負契約において、正式に書面で契約を締結する前に業務が進み始めることがあります。特に、設計業務の場合は、契約前の営業行為としての無償か、契約に基づく設計業務として有償かが争いとなることがあります。その場合、当事者間のやりとり、特に、業務の内容や報酬額等の契約の主要な部分が特定され、当事者間において確認されていたかが重要となります。本件では、これらの事実関係を詳細に認定し、契約の成立を認定しました。そして、出来高については、設計監理業務全体における基本設計の割合(設計業務80%、基本設計29%)を前提に、業者が実際に行った業務の割合を認定し(専門家調停委員が算定)、最終的な報酬額を算出しました。
(2024.1.2)
1 事案の概要
建物所有者が、隣地建物所有者、解体工事施工者、新築工事施工者に対し、隣地のビル建設工事に伴う土工事(山留工事等)により、外壁スレートが割れ、建物全体が傾き、室内の壁紙に亀裂が入り、隙間が開いたなどとして、共同不法行為に基づく損害金の支払を求めた事案。
主たる争点は①解体工事での外壁損傷の発生、②山留工事による建物傾斜の発生、③共同不法行為責任である。
2 裁判所の判断
(1)解体工事による外壁の損傷について
解体前の写真がなく、解体工事中の写真からは、解体前に外壁のスレートが割れていなかった、あるいは存在していたと認定できず、建物自体、昭和41年に新築され、本件解体工事の際には築49年であったことなどから、経年等により割れるに至ったものである可能性を否定することができないなどとして、解体業者の責任を否定した。
(2)山留工事による建物傾斜の発生について
日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説」には、横矢板の設置に際しては、横矢板の裏側に裏込め材料を十分に充填した後、親杭と横矢板との間にくさびを打ち込んで裏込め材の締固めと安定を図る旨の記載がある。
本件建物及び隣地新築ビルに近接するX1地点の地盤のN値は0ないし1程度であること、第1期山留工事では、隣地境界線から20ないし25cmほど離れた地点を少なくとも1.6m程度掘削し、H鋼の大きさを100mm×100mmとする親杭横矢板工法を採用したこと、横矢板の設置後に裏込め土の充填や親杭間にくさびを挿入するなどの措置は講じなかったことが認められるところ、これらの事実関係に加えて、専門家調停員本件意見書における意見も踏まえれば、第1期山留工事は、本件建物全体に影響を及ぼすとまではいえないが、山留壁の変位を許容し、隣接地盤の緩みを生じさせ、本件建物の基礎の変位を招く可能性のあるものであったと認められる。
そして、第2期山留工事では、山留壁より隣地境界線側を掘削しているのに、掘削する前又は掘削に合わせて掘削箇所を合板で押さえる措置を講じていないことが認められるところ、専門家調停委員の意見も踏まえると、第2期山留工事は、本件建物の全体に影響を及ぼすとまではいえないものの、本件建物の東側の基礎直下の土が側方からの支持力を低下させ、又は側方から応力を開放して本件建物の基礎の沈下を生じさせる可能性のあるものであったと認められる。
上記認定したところに加えて、専門家調停委員の意見を総合すれば、本件山留工事によって、少なくとも本件建物の東側基礎部分が本件山留工事によって沈下した可能性があると認められる。そして、上記認定事実によれば、本件建物の床下の畳部を支える大引きや床板と、土台、柱、壁は縁が切れていたこと、本件山留工事後の平成28年2月13日の調査時点で本件隙間があることが確認されていたこと、本件新築工事前の平成27年3月に本件建物には賃借に先立ち現状確認がされ、開店準備のための畳交換などが行われていたことが認められる。そして、上記の賃借と開店に至るまでの経緯の後において本件隙間が残っているとは通常考え難いから、本件山留工事の約3ないし4か月前には本件隙間は存在しなかったものと推認される。以上に加えて、専門家調停委員の意見も踏まえると、上記の本件山留工事によって本件建物の東側基礎が沈下する可能性と、本件山留工事の約3ないし4か月以後に本件建物の1階東側に本件隙間が発生したこととは整合するものといえる。
これまでに説示したところを総合すると、本件においては、経験則に照らし、本件山留工事が本件隙間の発生を招来したことに関しては、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度に立証されているものといいうるから、本件山留工事と本件隙間の発生との間には因果関係があると認められる。
(3)共同不法行為の成立について
建物所有者は、一級建築士の資格を持ち、隣地建物の設計監理者であるというだけでなく、所有者、発注者であるという地位を併せ持ち、かつ、建築の専門知識をもって現場において、常時、直接本件山留工事を確認していたなど具体的な事実関係の下では、隣地所有者としては、施工業者の本件山留工事の施工によって周辺地盤に影響を与えることのないように注意すべき義務を負い、第1期山留工事に接した際には、自立式ではなく切梁式の土留め工法や、より大きなH鋼の使用を検討し、施工業者に是正を指示すべき義務を負っていたというべきである。それにもかかわらず、これを怠り、施工業者の施工を許容していたと評価せざるを得ないから、上記注意義務に違反したと認めるほかない。
したがって、隣地所有者には、過失があり、施工業者による本件山留工事の施工と隣地所有者による注意義務違反とは客観的に関連共同するから、共同不法行為(民法719条前段)に基づき、連帯して、本件山留工事によって発生した前記隙間等につき損害を賠償すべき義務を負う。
3 コメント
本件のように、近隣での工事により建物が傾いたり、壁に亀裂が入ったりするなどの被害が生じる事例があります。その場合、工事前の建物状況を写真等で保存しておくと、工事前後の対比ができるので、立証がしやすくなります。施工会社が事前に施工前の状況について写真撮影を求めてくる場合もありますが、施工会社が求めてこない場合は、施工業者に依頼したりることも、自ら写真を撮影しておくことも必要です。
本件は、隣地所有者の責任も認められましたが、これは、隣地所有者が設計監理者であり、現場で指示を出していたという特殊事情により認められたものと考えられます。
(2022.12.4)
1 事案の概要
本件は,鉄筋コンクリート造,地下1階,地上4階建ての建物の建築の依頼をした施主が、請負業者に対し,サッシ付近の錆やガラスのひび割れなどが生じたことが施工上の瑕疵であると主張して,瑕疵担保責任に基づき損害賠償を請求した事案。主たる争点は、瑕疵の有無と損害額。
2 裁判所の判断
(1)サッシの錆止めの瑕疵の有無について
窓枠がスチールサッシで錆が発生しやすいことから二液混合のウレタン防水処理が必要であるが、二液混合のウレタン防水は混合が不十分であると効果が十分でないことがあること、引き渡しから3カ月で錆が発生していることなどから、防水処理等の施工に瑕疵があるとした。
(2)ガラスの施工の瑕疵について
窓ガラスの割れについては、ペアガラスの内側に破片が落ちているから、ガラスをサッシにはめ込む際に割れたものと推認し、被告の地震による割れの抗弁を排斥して施工の瑕疵を認めた。
3 コメント
本件では、補修方法も争点となり、請負業が最も安価な方法で補修がなされるべきと主張しましたが、被告が主張するより安価で合理的な方法が具体的ではないとして、施主側の主張する補修方法を採用しました。なお、補修方法は、より安価方法がある場合は、その方法による補修がとられるべきであるとするのが一般的です。
(2022.12.3)
1 事案の概要
本件は、旅館を運営する会社から工事を依頼された業者が、旅館に附属する露天風呂の造設工事、旅館建物内及びその周辺の改修工事並びにその追加工事を請け負い、各工事を完成させて引き渡したにもかかわらず、請負代金全額を支払わないと主張して、旅館運営会社に対し、工事代金及び遅延損害金を請求した事案。
主たる争点は、工事に建築基準法違反があり代金請求が信義則に反するか、
2 裁判所の判断
(1)建築基準法違反があった場合に代金請求が可能かについて
特定の建物の建築等についての請負契約に建築基準法違反の瑕疵があるからといって、直ちに当該契約の効力を否定することはできないが、当該契約が建築基準法に違反する程度(軽重)、内容、その契約締結に至る当事者の関与の形態(主体的か従属的か)、その契約に従った行為の悪質性、違法性の認識の有無(故意か過失か)などの事情を総合し、強い違法性を帯びると認められる場合には、当該契約は強行法規違反ないし公序良俗違反として私法上も無効とされるべきである(東京高判昭和53年10月12日、同平成22年8月30日)。
本件では、本件契約において建築が予定されていた露天風呂は、建築基準法6条1項4号所定の建築物に該当し、その建築には、当該建築につき同条による建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならず、工事完了時には同法7条により当該建築物が法令に適合するかどうかについて検査を受けなければならないが、本件露天風呂工事は、事前に建築確認を受けずに施工され、工事完成後の完了検査も経ていないもので、上記建築基準法の規定に明確に違反しており、旅館に附属する露天風呂として不特定多数の公衆の利用が予定されていたにもかかわらず、建築基準法所定の安全基準に合致していることが全く担保されていなかったことになるから、違反の程度は重いというべきである。
そして、本件では双方が、建築基準法に違反する違法な行為であることを認識しつつ上記行為を行ったことは明らかであるが、原告が、被告に対し、違法行為を求められても従わざるを得ないような従属的な立場にあったとまでは認められない上、原告は、建設業法3条1項の許可を受けていないにもかかわらず、本件契約を締結して本件露天風呂工事を施工したもので、その行為は、建築基準法のみならず建設業法にも違反しており、悪質であると言わざるをえない。
これらの事情を考慮すると、本件露天風呂工事の施工自体が建築基準法の規定に違反し、強い違法性を帯びるものであるといえるから、本件契約は、強行法規ないし公序良俗に違反するものとしてその効力を否定されるべきものである(被告は上記露天風呂を取り壊す予定であること、原告は本件契約に基づく請負代金のうち1100万円を既に受領しており、同金員は不法原因給付として被告への返還義務はないと解されることから、本件契約の効力を否定することによって、当事者の一方を不当に利する又は害することにもならないというべきである。)。したがって、原告の被告に対する本件露天風呂工事に係る残代金請求には理由がない。
3 コメント
施主から違法建築を依頼され、請負業者が止む無くこれを受け、違法建築が発覚した後に施主がこれを否定して争いになる場合があります。本件も同様の事案ですが、裁判所は、最判を引用して、建築基準法違反が直ちに私法上契約が無効となるものではないとした上で、本件では、請負業者が建設業法の許可を得ておらず、工事対象物件が不特定多数の人が訪れる旅館の風呂という事情もあることなどから、建築確認申請が出されず完了検査設けていないのは重大な違法があるとし、請負業者側も違法建築を受け入れざるを得ないような弱者ではないから工事を行ったことは悪質であり、契約自体が公序良俗違反で無効であるとし、請負代金の残代金の請求を否定した。なお、施主側も違法を認識していたことから不法原因給付として既払金の返還請求はできません。
(2022.12.1)
1 事案の概要
本件は、不動産業者から中古建物を購入した買主が、当該建物の店舗部分の柱及び梁が腐食しており、また、当該店舗部分に設置された化粧洗面台、便所及び手洗所から水が出ない状況であったことから、選択的に、①本件各瑕疵は、民法570条の「隠れた瑕疵」に当たるとして瑕疵担保責任に基づく損害賠償として、②売主は、各瑕疵の存在を当然知り得る立場にあり、原告に対し、これを告知すべき義務があったにもかかわらず、故意又は過失によりこれを怠った(告知義務違反)として債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として、売主に対し、柱等瑕疵に係る改修工事費用、水道瑕疵に係る復旧工事費用、各瑕疵への対応のために要した交通費、各瑕疵への対応により発生した逸失利益等の支払いを求めた事案。
2 裁判所の判断
(1)瑕疵担保責任の有無について
民法570条の「瑕疵」とは、当該契約の目的物の通常有すべき品質、性能を欠く場合をいうところ、本件売買契約のような中古建物の売買では、売買契約当時、一定程度の損傷が存し、その購入後、一定の修理等を要することを見込んで購入代金を決定するものであるから、当該建物の築年数や構造等に照らして通常有すべき品質、性能を基準として、かかる程度を超える損傷がある場合に「瑕疵」があるものと認めるのが相当である。
本件では、築24年の木造住宅で、経年劣化等により一定程度の損傷が存在することは当然といえるところ、売買契約には特約として、建物には経年劣化、機能低下、破損、ヒビ、汚れ等が見られるものの、買主はこれを容認し、売主に対して異議を述べない旨定められていることからすれば、経年劣化等により一定程度の損傷が存在することは、売買契約締結の前提としていたものと認められる。そして、売買契約当時においても一定程度の柱等の腐食があった可能性は否定できないが、その柱等の腐食の程度が建物の築年数や構造等に照らして通常有すべき品質、性能を基準として、かかる程度を超える損傷であったとまでは認められない。よって、柱等の瑕疵は民法570条の「隠れた瑕疵」に当たらない。
また、水道瑕疵の原因は、どの時点の、誰の行為により、洗面台等に水を供給していた配管が取り外されるなどしたのかを特定することはできないことから、そもそも水道瑕疵が売買契約の締結時点において存在していたか否かも不明であるといわざるを得ないのであって、水道瑕疵は民法570条の「隠れた瑕疵」に当たらない。
(2)説明義務違反について
契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないが、不法行為による賠償責任を負うことがある(最高裁平成23年4月22日第二小法廷判決・民集65巻3号1405ページ参照)。
本件では、瑕疵担保責任の有無で検討したとおり、柱等の腐食の程度が建物の築年数や構造等に照らして通常有すべき品質、性能を基準として、かかる程度を超える損傷であったとまでは認められず、建物に経年劣化等により一定程度の損傷が存在することは、売買契約の締結に先立ち、買主に対して説明済みであると認められるから、上記信義則上の説明義務は果たしているものと認めるのが相当である。また、水道瑕疵に関しても、そもそも水道瑕疵が本件売買契約の締結時点において存在していたか否かが不明である以上、売買契約の締結に先立ち、売主が水道瑕疵に係る告知義務を負っていたとはいえない。
よって、売主に説明義務違反は認められない。
3 コメント
中古建物について通常有すべき性質とは、その築年数や構造により異なると考えられますが、本件では、築24年の木造建物であり、売買契約に経年劣化による損傷等については買主が了承していたという事情もあることなどから、隠れた瑕疵に当たらず、説明義務違反もないとしています。売買金額も当初金額から減額して契約が成立し、建物価格も300万円程度であったことも判断に影響を与えているかもしれません。
(2022.11.27)
1 事案の概要
本件は、食品の卸業をする会社が土地建物の賃貸、分譲等を業する会社から土地を購入したところ、当該土地には売買締結時に明らかでなかった土壌汚染及び埋設物があったと主張して、売主の瑕疵担保責任(民法570条)、又は債務不履行(売買契約上の表明保証違反及び付随的義務である説明義務違反)に基づき、損害賠償請求した事案。
2 裁判所の判断
(1)売主が瑕疵担保責任を負うか
ア 地中埋設物に関する瑕疵について
買主は、本件土地が長年にわたってJが所有し、一時期、J用地として使用された後、20年以上も空地又は鉄製の管材、塩ビパイプ、ケーブル長尺物等の資材置場として利用されてきた土地である旨の記載がある本件地歴報告書を受領している上、遅くとも昭和63年ころから、本件土地の隣接地で営業をしていたのであるから、上記のような本件土地の利用状況や、本件土地が、Jの送電のための鉄塔、鋼材の売買等を目的とするH株式会社の工場及び建設機械の修理・製作・販売を目的とするI株式会社の工場等に隣接していることをも十分認識していたと考えられる。これに加えて、本件特約5項において、少なくとも残置物として「⑤旧鉄塔基礎⑥水道埋設管及びガス埋設管⑦木柵⑨旧建物(寮、資材置場ですが登記記録は存在しておりません。)基礎等」が確認されていた旨の記載がされていたことからすれば、当事者双方は、本件売買契約締結時において、本件土地は工場用地として利用されていた地区内にある土地であって、これまでの利用状況等からして、従前、保管されていた資材の一部や存在した建物の基礎等、何らかの埋設物が地中に残存していると共に、それらによる何らかの土壌への影響が残っている可能性があるものと認識・想定していたものと考えられる。
そうすると、本件土地に、コンクリート杭、コンクリート製の側溝、ケーブル、木くず、ゴミ等の本件埋設物が埋まっていたことは、契約当事者間の合意に基づき予定されていた品質又は性能を欠き、隠れたる瑕疵に該当するものとは認められない。
イ 土壌汚染について
買主は、売主から本件売買契約の際に、本件土地から第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)は検出されず、第2種特定有害物質(重金属等)及び第3種特定有害物質(PCB)は全て基準に適合しており、土壌試料中に油臭・油膜は確認されなかった旨の記載がある本件調査報告書を受領しているから(前記1(1)エ、カ)、当事者双方は、本件売買契約締結時において、本件土地に深刻な土壌汚染はないものと認識していたものと考えられる。
そして、鑑定の結果によれば、少なくとも、本件試し掘りがされた部分については油分も確認されていないことからすれば、これを越えて、本件土地の広範囲の土壌中に多量の油分が広がり、油によって土壌が汚染されているとは認められない。
また、中央環境審議会土壌農薬部会土壌汚染技術基準等専門委員会が平成18年3月に発出した「油汚染対策ガイドライン-鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方-」によれば、油汚染問題に対する対応の基本は、地表や井戸水等の油臭や油膜という、人が感覚的に把握できる不快感や違和感が感じられなくなるようにすることとされており、一般の工場・事業場の敷地などにおいては、舗装などによる地表の油臭の遮断と油膜の遮蔽が基本とされているところ、本件土地のうち、油分が認められた全ての地点において、地表では油膜は認められなかったから、油膜を遮蔽する対策が必要であるとはいえない。
油臭についても、本件ガイドラインによる0~5までの6段階のうち、段階2の油臭が認められたのは、地点アの深度1メートル、Eの深度1.5メートルの2地点のみであったものであり、その余はいずれも段階1であったところ、段階1の油臭については、通常、何らかの対策が必要であるとは認められない。段階2についても、必ずしも対策が必要であるとはいえないところ、原告は、本件土地を倉庫の敷地として使用するため、当初から、本件土地に対する地盤改良工事や地表の舗装工事を予定していたというべきところ、油臭についても、設置費用が約13万円程度の油防止シートを倉庫の基礎の下に設置するという簡易な対策を施すことによって、現在、特段の問題もなく本件土地上の倉庫で小麦粉問屋業を営んでいることからすれば、土地を裸地のまま利用する際に検討されるべき土壌の掘削除去や油含有土壌中の油分を分解あるいは抽出する浄化などの対策が必要であるとまでは認められない。そうすると、本件土地の南東部分のうち、隣接地との境界付近部分の深さ1~1.5メートル付近の土壌には油分が含まれていたことは、契約当事者間の合意に基づき予定されていた品質又は性能を欠き、隠れたる瑕疵に該当するものとは未だ認められない。
(2)売主に表明保証義務違反の有無について
契約書の特約には、現在確認されている残置物として、旧鉄塔基礎、水道埋設管及びガス埋設管、木柵、旧建物(寮、資材置場ですが登記記録は存在しておりません。)基礎等については不明との記載がされているのであるから、むしろ、本件土地には埋設物が存在する可能性があることが指摘されているというべきであって、被告が、本件埋設物が存在しないことを表明し保証したとは認められない。
(3)売主の説明義務違反の有無について
売主は、買主に対し、埋設物については、特約5項において、それが存在する可能性について言及した上で、特約6項において、その処理の分担を定めているものである。また、土壌汚染については、被告は、原告に対し、本件売買契約時に本件地歴報告書及び本件調査報告書を交付しているところ、本件調査報告書による調査が、本件土地を売買するに当たって、通常行うべき程度に欠けるほど不十分なものであったと認めるに足りる証拠はない。よって、売主に本件売買契約の付随的義務である説明義務違反があったとは認められない。
3 コメント
裁判所は、隠れた瑕疵の有無については、買主も当該土地の利用状況等についても認識しており、一定の地下埋蔵物があるであろうことは認識することができ、契約書にも一定の埋蔵物がある可能性についても言及しており、汚染についても客観的調査結果を前提に油汚染対策ガイドラインを参照しつつ、何等かの対策が必要な状態ではないとし、結果として隠れた瑕疵に当たらないとしました。
また、説明義務違反については、売主が地歴報告書と土壌汚染調査報告書を提出していることから説明義務違反はないとしました。
民法の改正により、瑕疵担保責任は契約不適合責任と変更になりましたが、結局のところ、契約に至る経緯その他から契約時の当事者の合理的意思を推認して合意内容を確定し、契約不適合があったか否かを破断することになります。
(2022.11.26)
1 裁判所の判断
請負契約における注文者の請負代金支払義務と請負人の目的物引渡義務とは対価的牽連関係に立つものであるところ、瑕疵ある目的物の引渡しを受けた注文者が請負人に対して取得する瑕疵修補に代わる損害賠償債権は、上記の法律関係を前提とするものであって、実質的、経済的には、請負代金を減額し、請負契約の当事者が相互に負う義務につきその間に等価関係をもたらす機能を有するものである。しかも、請負人の注文者に対する請負代金債権と注文者の請負人に対する瑕疵修補に代わる損害賠償債権は、同一の原因関係に基づく金銭債権である。このような関係に着目すると、上記両債権は、同時履行の関係にあるとはいえ、相互に現実の履行をさせなければならない特別の利益があるものとはいえず、両債権の間で相殺を認めても、相手方に不利益を与えることはなく、むしろ、相殺による清算的調整を図ることが当事者双方の便宜と公平にかない、法律関係を簡明にするものであるといえる(最高裁昭和52年(オ)第1306号、第1307号同53年9月21日第一小法廷判決・裁判集民事125号85頁参照)。
上記のような請負代金債権と瑕疵修補に代わる損害賠償債権の関係に鑑みると、上記両債権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属している場合に、本訴原告から、反訴において、上記本訴請求債権を自働債権とし、上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁が主張されたときは、上記相殺による清算的調整を図るべき要請が強いものといえる。それにもかかわらず、これらの本訴と反訴の弁論を分離すると、上記本訴請求債権の存否等に係る判断に矛盾抵触が生ずるおそれがあり、また、審理の重複によって訴訟上の不経済が生ずるため、このようなときには、両者の弁論を分離することは許されないというべきである。
そして、本訴及び反訴が併合して審理判断される限り、上記相殺の抗弁について判断をしても、上記のおそれ等はないのであるから、上記相殺の抗弁を主張することは、重複起訴を禁じた民訴法142条の趣旨に反するものとはいえない。
したがって、請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に、本訴原告が、反訴において、上記本訴請求債権を自働債権とし、上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許されると解するのが相当である。
(2022.11.23)
1 事案の概要
本件は、請負業者が、注文主に対し、建物の大規模修繕工事請負契約に基づき残代金1560万円及びこれに対する支払済みまで商法所定年6%の割合による遅延損害金を請求する事案である。
2 裁判所の判断
(1)工事の完成について
工事の完成とは、工事が予定された最後の工程まで一応終了したことを指すと解され、最後の工程まで一応終了している場合は、何らかの瑕疵修補が必要であったとしても、それは工事が完成したが瑕疵がある場合に当たるというべきであるとして、本件については、工事の予定された最後の工程まで終了して引渡しをしたと認められるとした。
(2)各瑕疵について
スロープの縁と道路の角度等は、いずれもよほど注意して見なければ分からない程度のわずかなものであって、本件建物の美観やスロープとしての性能を損なうようなものではないことが明らかであるから瑕疵とはいえない。
駐輪場は、居住者が自転車を置くためのスペースであるから、自転車を置くことに支障を来すような不陸があってはならないが、屋内のロビーや廊下、居室の床面とは異なり、鏡のような平坦さにより構成される美観を要求される場所ではなく、駐輪場にはわずかな凹みがあるだけであり瑕疵とはいえない。
バルコニーも、個々の居住空間に属するという点においては駐輪場よりも美観を要求されるレベルは高いといえるが、基本的に、屋外スペースとして洗濯物干しや植木鉢を置く等の用途に供される場所であり、同様に鏡のような平坦さにより構成される美観を要求される場所ではなく、バルコニーにはわずかな凹みがあるだけであり瑕疵とはいえない。
屋上パラペットに塗りむらがあとしても、屋上パラペットは、住民が通常目にすることはなく、美観を要求される部分でもないといえるから、塗りむらが瑕疵とはいえない。
なお、本件建物が通常よりも高度の美観を要求されるデザイナーズマンションであることを売り物にしている物件であるとしても同様である。
(3)同時履行の抗弁権について
瑕疵が極めて軽微なものであり、瑕疵の修補に代わる損害賠償債権をもって報酬残債権全額の支払を拒むことが信義則に反する(最高裁判所第三小法廷判決・平成9年2月14日民集51巻2号337頁参照)というべきであるから、同時履行の抗弁を主張することはできない。
3 コメント
各争点について、一般的な基準に基づき判断しています。瑕疵については、美観が重要視される部分については美観も重要な要素になりますが、機能性が重視されるものについては、機能上問題なければ瑕疵がないと判断される傾向にあります。
(2022.11.22)