誠実・公正・迅速 あなたの目線で紛争の適切な解決に努力します。
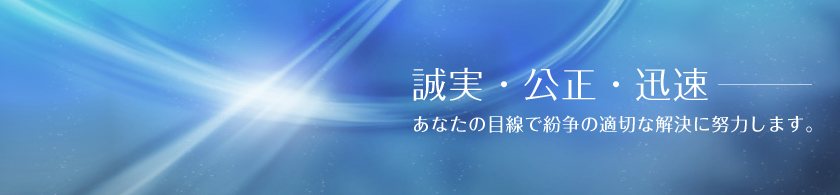
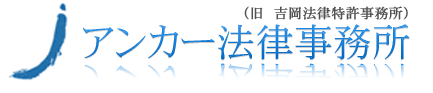
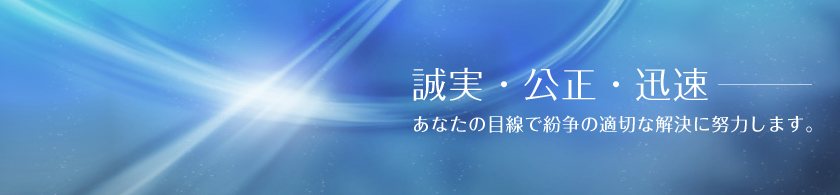
1 事案の概要
本件は、マンション管理組合が、区分所有者居室内の浴室から階下に水漏れが生じており、このことが区分所有法6条1項所定の区分所有者の共同の利益に反する行為に該当すると主張して、区分所有者に対し、主位的に区分所有法57条1項に基づき、浴室について防水工事を施工することを求め、予備的に区分所有法6条2項、57条1項に基づき、原告が本件浴室について防水工事を施工することの承諾等を求めた事案である。
主たる争点は、区分所有者居室内の浴室から漏水が生じているかである。
2 裁判所の判断
(1)区分所有者居室内の浴室からの漏水の有無について
被告である区分所有者は、管理組合又は漏水被害のあった区分所有者等の代理人弁護士から、相応の根拠(調査液注入試験(ポスト工法)、注水試験(W.I.T)及び水圧・散水試験の各方法により行われ、前2つの試験により漏水確認)に基づき漏水の補修工事を施工することを求められても一向にこれに応じようとしないのであって、被告区分所有者居室内の浴室からの漏水により、少なくとも階下の区分所有建物の浴室天井部に継続的に漏水を生じさせており、ひいてはマンション自体にも損傷を生じさせているものである。そうすると、被告区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしており、今後もその行為をするおそれがあるといえるから、管理組合は、本件マンションの区分所有者の共同の利益のため、その停止等のため必要な措置を執ることを請求することができる(区分所有法6条1項、57条1項、3項)。そして、浴室について防水工事を施工することは、上記の必要な措置に当たるといえる。
3 コメント
区分所有法6条1項は、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」と定めています。同条違反としては、管理規約に違反した専有部分を利用した場合(民泊、風俗営業等)、専有部分から悪臭、騒音が生じた場合、共用部分が棄損された場合等が挙げられ、多くの訴訟が提起されていますが、本件は、漏水により階下の住人等が被害に遭ったという事案で、少し特殊な事案です。
本件では、階下の住人が直接、不法行為に基づく損害賠償等を請求することも考えられましたが、複数の住民に被害が生じており、漏水という性質からマンション自体にも損傷が生じているということで、管理組合が原告となって訴訟を提起し、裁判所も共同の利益に反すると判断したものと考えられます。
(2024.1.21)
1 事案の概要
本件は、マンションの区分所有者が、①管理組合に対し、管理組合が自治会に団体として加入し、管理費から自治会費を支払う旨の管理規約及び管理組合が自治会を脱退する場合には全体総会の特別決議を経る旨の管理規約がいずれも無効であることの確認請求、②管理組合が各定期総会において、管理費から自治会費を支払う内容の予算案を承認した各決議がいずれも無効であることの確認請求、③区分所有者が管理組合に支払った管理費のうち、区分所有者が自治会を退会した日以降に管理組合が支払った自治会費相当額について不当利得に基づく返還請求をこうした事案である。
主たる争点は、①自治会に関する各条項の定めが管理組合の目的の範囲内といえるか、②実質的に区分所有者の自治会退会が制限されているかである。
2 裁判所の判断
(1)自治会に関する各条項の定めが管理組合の目的の範囲内といえるかについて
自治会は、管理組合が管理する建物等の対象範囲と活動地域が一致し、自治会の基本方針に各マンションの生活環境の改善・向上のための活動が含まれ、自治会は各マンションに係る防災・防犯・清掃活動、各マンションの価値の維持・向上に資する近傍の美化活動・住環境改善活動を行っていることからすると、自治会は、管理組合の建物等の管理に含まれる活動を基本方針とし、実際にも各マンションの建物等を維持していくために必要かつ有益な活動を行う団体であるといえる。したがって、自治会に加入することを被告の規約に定めることは、建物等の管理に関する規約として被告の目的の範囲内ということができる。
また、自治会への加入が建物等の管理に必要かつ有益であるといえる以上、任意加入団体としての自治会が管理組合の目的に含まれない他の活動を行っていた場合であっても、本件自治会への加入が被告の目的の範囲を逸脱することとなるものではない(なお、イベント(催事)やサークル活動についても、その目的・内容によっては、マンション及び周辺の居住環境の維持向上に資する活動として、被告の目的に含まれる場合があり得るものと解される。)。
もっとも、管理組合と自治会との関係に照らして、自治会への加入及び脱退を定める管理規約の各条項が、区分所有法に定められた管理組合の規約事項を潜脱する意図で定められたことが明らかであるなどの特段の事情が認められる場合には、管理規約の各条項の効力が否定される余地もないとはいえない。
本件では、管理組合と自治会は、共通の目的を有する関係にはあるものの、自治会は管理組合の業務に協力し、その対価としての性質を有する自治会費を受領する一方、自治会の活動内容はその基本方針に沿って自治会が独自に策定しているということができる。そうすると、管理組合と自治会は協力関係にある別個の独立した団体であるといえるから、自治会への加入が管理組合の規約事項を潜脱する目的で定められたものと評価することはできない。
(2)実質的に区分所有者の自治会退会が制限されているかについて
管理組合が自治会に支払う自治会費は、管理組合が団体として支払義務を負う会費であり、観念的には構成員である区分所有者が拠出した管理費がその原資に含まれ得るものであるとしても、そのことによって管理組合の一構成員である区分所有者が自治会に自治会費を支払ったこととなるものではない。
もっとも、管理組合の支払う自治会費が、管理組合の組合員の数や戸数に応じて算出されるなど組合員の支払うべき自治会費を管理組合が代わりに支払っているといえる実態が存在するのであれば、形式的には団体として負担する自治会費であったとしても、その実質は各組合員が負担すべき自治会費を管理組合が代理徴収して支払ったものと評価する余地があるといえる。
本件においては、管理組合が支払った自治会費は、各年度ごとに自治会から予算要求を受け、自治会の活動内容を踏まえて定められた金額であると認められ、管理組合の組合員数や各マンションの戸数に対応して定められたことをうかがわせる証拠はない。また、管理組合細則において、管理組合の支払う自治会費は、管理組合が自治会に業務の一部を委任し又は管理組合業務の補助を受けることの対価としての性質を有することが確認され、そのことが管理組合と自治会との間で確認されていることからすれば、管理組合の負担する自治会費は、管理組合の組合員が支払うべき自治会費を代わりに支払ったものではなく、自治会の行う活動のうち管理組合業務に関連する活動の対価の位置づけで支払われているものということができる。そうすると、管理組合が支払う自治会費は、自治会の活動内容に即して、自治会からの予算要求を受けて支払われているもので、自治会の被告の業務に関連する活動の対価として位置付けられているものであるから、管理組合が組合員の支払うべき自治会費を代理徴収して支払っているものと評価することはできない。
よって、管理組合の組合員の自治会に対する脱退の自由を侵害することにはならない。
3 コメント
管理組合の管理費と自治会費の徴収、管理が峻別されていれば、本件のような問題は生じませんが、本件では、管理費として徴収した中から自治会費が支払われていることから、それを定めた管理規約の有効性が争われるとともに、自治会からの脱退の自由が侵害されているかが争われました。
裁判所の判断は、管理規約は有効であり、区分所有者が自治会から脱退する自由も侵害されていないと判断しましたが、大きな理由は、自治会の目的が管理組合の目的を包含しており、支払われた自治会費が管理組合の組合員数や各マンションの戸数に対応して定められた金額ではなく、管理組合から自治会に対する支払は管理組合業務の助力に対する対価であったという点が重要であったと考えられます。
なお、区分所有者が管理組合や自治会に対し、管理組合が管理費と一緒に徴収した自治会費の返還を求めた裁判例がありますが、こうした事案では、管理組合が自治会費名目で徴収しいるという事実関係を踏まえ、区分所有者の主張が認められています(東京地判平成19年9月20日、東京高判平成21年3月10日(自治会に対して返還を求めた事案))。一方、本件と同様に、管理組合が管理規約に基づき町会費を負担していたという事案では、町内会費を納入し、町内会に協力することも管理組合の業務に含まれるとして管理費から町会費を支出する旨の総会決議を有効としています(東京高判平成24年5月24日)。
(2024.1.8)
1 事案の概要
本件は、マンションの管理組合が、前任の理事長で区分所有法25条所定の管理者であった者に対し、同人が区分所有者らから特別修繕費の回収を怠った結果、特別修繕費債権が時効消滅したことにより同額の損害を被ったと主張して、債務不履行(善管注意義務違反)に基づく損害賠償請求をした事案である。
主たる争点は、前管理者の善管注意義務違反の有無、損害である。
2 裁判所の判断
(1)前任管理者の善管注意義務違反の有無について
前管理者が特別修繕費の回収、管理をしていたと認められ、未払いを放置し、後任の理事長にも引き継がなかったことが善管注意義務違反に当たるとした。
(2)損害額について
後任の理事長が速やかに回収に当たれば時効にかからなかったであろうとの主張については、前理事長が未収金の事実について引き継がなかったことにより、その発見が遅れたのであるから前理事長と損害の間に相当因果関係があるとした。
3 コメント
管理者は善管注意義務を追うことになるから(区分所有法28条により委任の規定が準用される)、これに違反する損害賠償責任を負うことになります。後任への引継ぎも重要な業務となります。
(2024.1.6)
1 事案の概要
本件は、マンションの区分所有者が、専有部分にシロアリ被害が発生したのは、管理組合法人がマンションの床下土壌部分に係る管理義務を怠ったことによるものであり、また、同床下土壌部分の設置又は保存の瑕疵があったことによるものであると主張して、債務不履行又は工作物責任(民法717条1項本文)による損害賠償請求として、修理費用等及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
主たる争点は、①管理組合法人が管理規約に基づく共用部分の管理義務を負うか否か、②管理組合法人が民法717条1項の工作物責任を負うか否かである。
2 裁判所の判断
(1)管理組合法人が管理規約に基づく共用部分の管理義務を負うかについて
管理組合法人は、マンションの共用部分及び敷地の管理に関する事項は、総会の決議に基づくこととされ、保存行為を除いて区分所有者が単独でこれらの管理をすることはできないのであるから(区分所有法17条1項、18条1項、21条等)、管理組合法人はマンションの共用部分及び敷地の全般的な管理権限を有していることとなる。
また、マンションの管理機規約において、区分所有者である組合員が、マンションの共用部分や敷地等の管理や修繕に要する費用に充てるため、管理及び共益の費用や積立金を負担する義務を負い、毎月定額の管理及び共益の費用を被告に納入することとされるとともに、積立金でまかなうことができない修繕、保守の費用については、特別積立金又は臨時費を負担する義務を負うこととされているのであり、これは、区分所有者全員によって構成される管理組合法人が、マンションの共用部分及び敷地等の管理について、権限のみではなく責任を負うことをも前提として、その管理に要する費用については、第1次的には被告が負担し、最終的には被告を構成する区分所有者全員が同費用を負担することを明らかにしたものと解することができる。このような区分所有法の定めやマンション管理規約の上記各規定の趣旨に照らせば、本件マンションの区分所有者は、本件規約により、本件マンションの共用部分及び敷地の管理について、被告がその責任において管理すべきことを定めているものと考えることもできる。そうすると、管理組合法人は、マンション管理規約に基づいて、個々の区分所有者に対し、管理組合の業務の1つである共用部分及び敷地の管理を適切に行うべき義務を負い、これを怠ったことにより区分所有者が損害を被った場合には、当該区分所有者に対して債務不履行責任を負うと解する余地がある。
もっとも、シロアリ被害が判明する前に管理組合法人がマンションにおけるシロアリ被害の発生を予見することが困難であったことに加え、シロアリ被害を予防する防蟻処置を行う対象となるマンションの1階の床下部分を被告が日常的に管理すべき状態にはなかったのであるから、仮に、管理組合法人が、マンション管理規約に基づき、区分所有者に対してマンションの敷地である本件建物の床下土壌部分を適切に管理すべき義務を負っていたとしても、区分所有者の専有部分についてシロアリ被害が生じる可能性を予見することはできないというべきであり、上記管理義務の具体的内容として、専有部分たる建物に立ち入った上で専有部分の一部を損壊して防蟻処置をとるべき法的義務を被告が負っていたとまでは認められない。
(2)管理組合法人が民法717条1項の工作物責任を負うか否かについて
マンションの敷地はマンションの区分所有者の全員の共有に属するものであり、その占有者は区分所有者全員であって、管理組合法人がマンションの敷地、ひいては区分所有者の専有部分の建物の床下土壌部分を占有しているとは認められない。
また、管理組合法人は、マンション管理規約に基づいて、マンションの敷地等の管理を適切に行うべき義務を負うと解する余地があるものの、マンションは、その外部から区分所有者が専有する建物の1階の床下部分に出入りすることはできないという構造であり、当該建物を含むマンションの1階の床下の土を管理組合法人が日常的に管理することは極めて困難であることからすると、管理組合法人が、マンションの1階の床下部分について、占有者に準じた地位にあると評価することもできない。
3 コメント
裁判所の判断は、管理規約の内容からすれば、共用部分についての管理権限を有しているだけでなく責任も有していたと考えらえるが、シロアリ被害の予見可能性がなかったとして、防蟻処理義務はないというものでした。また、工作物責任については、管理組合法人が占有者にも占有者に準じた地位にも当たらないとしました。管理組合を被告として民法717条1項の責任が問われた裁判例が幾つかありますが、基本的には、共有部分は区分所有者全員の共有であるとして、管理組合の工作物責任を否定しています。
(2024.1.6)
1 事案の概要
本件は、マンションの管理組合の管理者が、マンションの施工を発注した会社(Y1)、マンションの設計・監理をした会社(Y2)及びマンションの施工者から営業譲渡を受けた会社(Y3)に対し、マンションの共用部分に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があると主張して、区分所有法26条4項に基づき、マンションの区分所有者のために、不法行為(Y1からY3に対し民法709条、被告Y1に対し更に同法715条、Y1とY2につき更に同法719条)に基づく損害賠償と遅延損害金を請求した事案である。
主たる争点は、①管理者の当事者適格の有無、②除斥期間の経過の有無、③出来高の評価である。
2 裁判所の判断
(1)管理者の当事者適格の有無について
管理者が、区分所有者に分割的に帰属する損害賠償請求権について、訴訟追行をし、その判決の効力が区分所有者全員に及ぶとするためには(民事訴訟法115条1項2号)、管理者は、上記損害賠償請求権につき、区分所有者全員から訴訟追行権限を授与されていることを要するものというべきであり、区分所有法26条4項の「区分所有者のために」とは「区分所有者全員のために」を意味するものと解される。
そして、本件各損害賠償請求権のような、共用部分に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があることを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、共用部分の共有持分権を有することに基づく請求権であり、区分所有者の共有持分に応じて分割的に帰属するものというべきところ、区分所有者が変動した場合、転得者たる区分所有者は、瑕疵の存在を知りながら、これを前提として区分所有権を買い受けたなどの特段の事情がない限り、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があることを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権を有するものと解される(最高裁平成17年(受)第702号同19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁参照)。
本件では、本件マンションの転得者が瑕疵のあることを知りながら、これを前提として区分所有権を買い受けたと認めるに足りる証拠はないから、本件各損害賠償請求権は、マンションの区分所有者全員に、その共有持分に応じて分割的に帰属するものと認められ、管理者は、本件各損害賠償請求権につき、「区分所有者のために」(区分所有法26条4項)訴訟追行するものということができる。
また、管理者による仮住まい費用及び移転費用といった専有部分に関する費用や、専有部分を含む建替費用に係る損害についての損害賠償請求権の行使は、マンションの共用部分に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があることを理由とする不法行為に基づく損害として請求しているのであるから、これらについても「共用部分等について生じた損害賠償金・・・の請求」(区分所有法26条2項後段)に当たるというべきであり、管理者がその「職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し」(区分所有法26条4項)、訴訟追行するものということができる。
(2)除斥期間の経過について
除斥期間の起算点は、加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には、加害行為の時と解され、加害行為たる建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務違反の終期は遅くともマンションの完成の時であり、遅くともY1が引き渡しを受けたときであり、区分所有者が引き渡しを受けたときではない。
そして、本件では、それから20年が経過しているので、各損害賠償請求権は民法724条後段により、いずれも消滅したものと認められるとし、原告の指摘する最高裁昭和63年(オ)第1543号、平成4年(オ)第1460号同4年10月20日第三小法廷判決・民集46巻7号1129頁は、瑕疵担保責任による損害賠償請求権に係る除斥期間を定めた規定(民法570条、566条3項)に関するものであり、その期間も規定ぶりも異なる民法724条後段には妥当しないとした。
なお、本件では、Y3が、スリーブ孔の補強工事を行うとともに迷惑料(補償金)を支払う意向を示していたことを認めることができるものの、新たな不具合の発覚後、管理組合とY1ないしY3は、スリーブ孔の補強工事の続行の可否や補償金の金額について対立していたことがうかがわれ、「確約書(案)」を含むY1らの通知には除斥期間の利益を放棄することを前提とする記載はないこと等からY1らが、除斥期間の利益を放棄したと認めることはできないとした。
3 コメント
区分所有法26条4項は、「管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる」と規定しています。そして、同規定の「区分所有者のために」とは、「区分所有者全員のために」を意味すると解されます。そうすると、マンションの管理者が区分所有法26条4項に基づき損害賠償請求訴訟の原告となるためには、マンションの区分所有者全員に損害賠償償請求権が帰属することが必要となりますが、本件では、マンションの数室が転売されていたことから、転得者に損害賠償請求権が帰属しているかが問題となりました。転得者が購入時に瑕疵のあるマンションとして購入していた場合等は、転得者に損害が観念できず、損害賠償請求権が転倒者に帰属しないものと考えられます。本件では、転倒者が瑕疵のあるマンションとして購入したと認める証拠はないとして、転倒者に損害賠償請求権が帰属することを認め、マンション管理者の原告適格も認めました。なお、本件では、瑕疵の修繕の際の仮住まい費用等の専有部分に関連する費用も請求していることから、区分所有法26条4項の「職務に関し」といえるかも争いとなりましが、これも認めています。
また、本判決は、民法724条後段の期間について、除斥期間であるとし、裁判外の権利行使では足りず、裁判上の権利行使をする必要があると解するのが相当であるとしましたが、裁判外の権利行使で足りるとした裁判例(前橋地裁高崎支部判平成31年1月10日)もあります。もっとも、改正民法では、民法724条後段の20年の期間は除斥期間ではなく時効期間と改正されましたので、民法改正後の事案については、時効中断の規定が適用されます。
(2024.1.5)
1 事案の概要
本件は、マンションの区分所有者が、マンションの管理組合に対し、居室内に発生した雨漏りについて共有部分の修繕を依頼したにも関わらず、管理組合がこれに応じなかったため、区分所有者が管理組合に代って調査及び修繕をしたと主張して、主位的に不法行為に基づく損害賠償請求、予備的に不当利得に基づく返還請求をした事案である。
主たる争点は、①漏水の有無、②不法行為の成否(故意・過失の有無)、③不当利得の成否である。
2 裁判所の判断
(1)漏水の有無について
管理組合が行った実施調査は、調査実施の前日の朝には相応の降雨があったものの、その後24時間以上降雨がない状態で実施されたものであり、しかも、当時は7月中旬で、この間の最高気温は約29.5度、日照も相応にあったことが認められる。これに加え、出窓が建物の4階東側に位置しており、東及び南からの日当たりが良好であることなどにも鑑みれば、管理組合実施調査の実施時における出窓周辺は相応に乾燥していた可能性があり、赤外線カメラ(濡れているところと乾いているところとの温度差等を調べるもの)によって漏水の有無を判断することは困難であった可能性があるから、管理組合実施調査は、漏水調査としては不十分な調査であったといわざるを得ず、その信用性は高くないというべきである。
他方、区分所有者実施調査は、出窓上部のコーキング部分等への散水と赤外線サーモグラフィーの併用による調査を行い、その結果として、コーキングの肌別れ部分に散水を行うと出窓上部のサッシ枠固定部から散水水が流れ出てくることから、外壁とサッシ枠接合面のコーキングの肌別れ部分から雨水が廻り込む漏水が発生しているなどと結論付けているのであり、その信用性は高いというべきである。
以上によれば、遅くとも区分所有者実施調査が行われた頃には、本件出窓上部の外壁とサッシ枠接合面のコーキングの肌別れ部分から雨水が廻り込む漏水が発生していたと認められる。
(2)管理組合の故意・過失による義務違反の有無について
管理規約の定めによれば、外壁は建物の共有部分であり、共有部分の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとされているから、管理組合は、出窓における漏水に関して、管理組合の責任と負担において管理修繕すべき義務を負っていたといえる。
しかし、管理組合は、出窓に関して、専門家(一級建築士)に依頼して調査を行っていたのであるから、調査義務を怠ったとはいえない。また、調査の結果、漏水の事実が認められなかったとされた以上、管理組合において、漏水の事実を認めずに修繕工事を行わなかったことをもって、故意又は過失により管理修繕義務を怠ったとまではいえない。
(3)不当利得の有無について
管理組合は、出窓における漏水に関して、管理組合の責任と負担において管理修繕すべき義務を負っていたところ、区分所有者の依頼・要求にも関わらず、管理組合が結果として必要にして十分な調査を行わず、修繕工事も行わなかったことから、区分所有者において、漏水の原因の特定及びその解消のために、区分所有者実施調査及びこれに基づく本件工事を行い、その費用を支出したことが認められ、管理組合は、区分所有者がこれらに関して負担した費用について、その損失において法律上の原因なく利益(不当利得)を得たというべきである。
(4)不当利得の額について
区分所有者の支出額が不相当であると認めるに足りる証拠はないから、同額が不当利得の額である。
3 コメント
管理規約により共有部分の修繕については管理組合が行うべきところ、管理組合が対応しなかったことから、区分所有者が自ら調査、修繕を行い、管理組合に当該調査委費用及び修繕費用を求め、これが認められたものであり、当然の結果であると考えます。
問題は、管理組合が調査を依頼した会社の調査方法が必ずしも適切ではなかったということです。赤外線による漏水調査は、雨漏りで浸入した雨水が蒸発するときの気化熱を利用して雨漏り箇所を特定するもので、散水調査後または雨が降った直後に調べる必要があり、裁判所もこの点を指摘しています。
(2024.1.5)
1 事案の概要
本件は、マンションの区分所有者から専有部分を賃借している者が、管理組合総会における円滑化法108条1項に基づくマンションの敷地売却決議には、区分所有法44条1項及び管理規約に違反する瑕疵があり、その瑕疵の程度も重大であるとして、上記決議の無効確認を求めた事案。
なお、円滑化法149条1項により権利消滅期日に借家権が消滅し、同法155条により借家人はその日までに貸室を明け渡さなければならなくなる。
2 裁判所の判断
区分所有法44条1項の趣旨は、同法において、区分所有者以外の専有部分の占有者も、建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならず(6条3項・1項、57条4項、60条)、また、建物又は敷地若しくは附属施設の利用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(46条2項)ことから、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者に対し、「会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合」に、集会の議事に関与する機会を与えるところにある。かかる同法44条1項の趣旨に照らせば、「利害関係を有する場合」とは、占有者が法律的な利害関係を有する場合であって、事実上の利害関係を有する場合を含まず、具体的には、占有者が直接に義務を負うことになる建物又は敷地若しくは附属施設の使用方法に関して集会の決議をする場合(それに関する規約の設定又は変更の決議をする場合を含む。)をいうと解される。
これを本件についてみると、円滑化法120条、122条、141条、147条、149条および155条等によれば、マンション敷地売却事業において、マンション敷地売却合意者(マンション敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者)らにより都道府県知事等の認可を受けて設立された敷地売却組合が、分配金取得計画を定めて都道府県知事等の認可を受け、その旨を公告するとともに、関係権利者に関係事項を書面で通知することにより、同計画に定められた権利消滅期日において、売却マンションが敷地売却組合に帰属し、売却マンションを目的とする所有権以外の権利は消滅し、売却マンション又はその敷地を占有している者が、権利消滅期日までに、敷地売却組合に売却マンション又はその敷地を明け渡さなければならない。
そうすると、本件マンションの敷地売却事業においては、前記前提となる事実のとおり、本件決議後に、マンション敷地売却合意者らにより港区長の認可を受けて設立された本件売却組合が、分配金取得計画を定めて港区長の認可を受け、その旨を公告するとともに、関係権利者に関係事項を書面で通知することにより、同計画に定められた権利消滅期日において、賃借人の本件居室に係る借家権が消滅し、賃借人は、権利消滅期日までに、本件売却組合に本件居室を明け渡さなければならないこととなる。したがって、賃借人は、本件決議によって、本件マンション又はその敷地若しくは附属施設の使用方法に関して直接に義務を負うことになるとはいえず、また、本件決議によって本件居室の明渡義務を負うことになるともいえないから、賃借人は、本件議案に法律上の利害関係を有すると認めることはできない。よって、本件決議に瑕疵はない。
3 コメント
区分所有法44条1項の「利害関係を有する」とは、占有者が法律的な利害関係を有する場合であって、事実上の利害関係を有する場合を含まず、具体的には、占有者が直接に義務を負うことになる建物又は敷地若しくは附属施設の使用方法に関して集会の決議をする場合(それに関する規約の設定又は変更の決議をする場合を含む。)をいうと解されています。本判決も同様に解して利害関係がないと判断しています。
なお、意見陳述権が認められる場合は、集会への出席自体が認められており、出席を認めず書面のみで意見陳述させることは本法違反と解されています。また、本法違反の決議は、意見陳述の機会を与えられなった占有者との関係では効力が及びないとかされています。
(2022.12.4)
1 事案の概要
本件は、マンションの区分所有者がが、管理組合に対し、自らの共有持分の修繕積立金を増額した管理組合の総会における管理規約の改正決議が無効であるとして、その増額分につき、既払金の返還等及び未払分の支払義務がないことの確認を求める本訴請求と、これに対し、管理組合が、当該区分所有者に対し、同改正決議は有効であるとして、改正後の管理規約に基づく未払の増額分の修繕積立金の支払等を求めた事案。
主たる争点は、①総会決議後の専有部分を取得した者は、総会決議を争うことができるか、②事務所部分の修繕積立金の増額(修繕積立金だけを見ると住居部分の1.5倍)が区分所有法30条3項に反するか、③将来請求の可否である。
2 裁判所の判断
(1)総会決議後の専有部分を取得した者は、総会決議を争うことができるかについて
本件決議は管理規約に定める修繕積立金につき、事務所部分についてのみ負担を増加させる変更決議であり、同決議は事務所部分の区分所有者からの特定承継人である原告に対してもその効力が及ぶため(法46条1項)、総会決議後に専有部分を取得した者も本件決議の効力を争うことができると解すべきである
(2)事務所部分の修繕積立金の増額が区分所有法30条3項に反するかについて
本件改正による事務所部分の修繕積立金の増額は、それ自体は住戸部分との不均衡を招くものといえるが、事務所部分と住戸部分の管理費の額も考慮すると必ずしも利害の衡平を害するものとはいえず(事務所部分が住居部分より割安)、このことは法30条3項が定めるその余の考慮要素を加味しても左右されない。なお、管理費と修繕積立金が使途目的を異にするが、区分所有法30条3項該当性の判断に当たり、これらを併せて検討することができないとは解されない。
(3)将来請求の可否について
区分所有者の未払いが3年程続いていることから、将来請求の必要性を認めた。
3 コメント
本判決は、区分所有建物を取得した者が自己に法的利害関係がある事項についての取得前の総会決議の効力を争うことができると判断しました。また、長期間修繕積立金の一部未払があったことから将来請求も認めました。
本件のように、管理費の額などに不均衡がありこれを是正(増額)する管理規約の変更が行われた場合、区分所有法31条1項後段の同意の有無の要否が争点となる場合もあります。
(2022.12.3)
1 事案の概要
本件本訴は、マンションの部屋を店舗として貸し出している区分所有者が、管理組合に対して、住居部分は住居として使用しなければならいとする管理規約の設定に関する総会決議は、専有部分を賃貸用店舗として使用収益する当該区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすにもかかわらず原告の承諾を得ることなく決議されたものであるから区分所有法31条1項に違反し無効であるなどと主張して決議無効を争うとともに、不法行為に基づく損害賠償請求した事案。
本件反訴は、管理組合が本訴に対応するための弁護士費用について、管理規約に基づき当該区分所有者に請求した事案。
2 裁判所の判断
(1)区分所有法31条1項に違反するか否かについて
ア 「特別の影響を及ぼすべき」場合に当たるかについて
202号室は、遅くとも原告が取得した時点で、台所や浴室も設置されていない事務所仕様の間取りとなっており、原告は、これを第三者に賃貸して収益を上げる目的で取得して以降、事業用建物として事業者に賃貸して収益を得ていたのであるから、事務所として使用できないとする管理規約が設定されると、原告の202号室に係る使用収益権は多大な制約を受け、原告が所期の目的を達することが困難になるとともに、これを住宅として使用する場合であっても相当多額の改装費用の支出を余儀なくされることとなる。そうすると、事務所として使用できないとする管理規約が設定されることによる原告の不利益は決して小さいものとはいえない。
また、管理規約の設定当時又はそれ以前に、202号室が事業者に賃貸されていたほか、2部屋についても事務所として使用されていた実態があるところ、このことにより、本件マンションの地上2階以上の居住者の住環境が格別害されていた様子はうかがえない。
以上のような202号室の現況や原告による同室の利用状況等に照らすと、事務所として使用できないとする管理規約を設定して原則住宅としての使用に限ることは、その必要性、合理性に比して、これにより原告が受ける不利益の程度が大きく、その不利益が一部の区分所有者の受任すべき限度を超えると認められる場合に該当するから、区分所有法31条1項後段の「特別の影響を及ぼすべきとき」に当たる。
イ 同意があったかについて
区分所有法31条1項後段の承諾は、管理規約の設定等の決議に際してこれに賛成する旨の意思表明をした場合もこれに含まれると解すべきところ、原告は、本件決議に先立ち、議決権行使を理事長に委ねる旨の委任状を提出したのであるから、これにより、原告の上記承諾があったものと解するのが相当である。
(2)管理規約に基づき弁護士費用を区分所有者に請求できるかについて
被告管理規約には、区分所有者等において規約違反等の事実があり、理事長が、当該区分所有者等に対してその是正等を請求するための訴えを提起した場合に、違約金として、これに要する弁護士費用等の支払を求めることができる旨を定められているに過ぎないところ、本件は、区分所有者が自身の規約違反行為の根拠とされた被告管理規約の設定を承認した本件決議が違法無効であって同規約の規定が無効であるにもかかわらず規約違反行為があるとして退去要求等を受けたと主張して管理組合に損害賠償を求める訴訟に対し、管理組合が応訴したものであって、区分所有者の規約違反行為を是正するための訴えがされているものではないから、被告管理規約が適用される場面ではない。また、区分所有者の行為が不法行為を構成するものではない。
そのような場合に、応訴した管理組合に管理規約に基づく弁護費用等の諸費用の請求を認めるとすると、本件マンションの区分所有者が管理組合の行為の違法を主張して訴訟提起することに対する萎縮的効果を生じさせ裁判を受ける権利を実質的に損ないかねない上、我が国においては、訴訟追行に要する弁護士費用を敗訴者の負担とすることを原則とするものではないことからすると、相当とはいえない。
3 コメント
マンションの専有部分の利用方法の制限に関し、区分所有法31条1項を根拠として争われる場合がありますが、本件では、「特別の影響を及ぼす」場合に当たるとしました。本件では、従前から事務所として賃貸されていた物件を賃貸目的で購入したこと、当該物件には風呂などの居住用の設備が設置されていないこと等から、区分所有者の不利益が大きいと判断したものと思われ、その点は妥当と思われます。また、同意については、総会決議に委任状を提出したことをもって承諾したものと認定しています。
そして、管理組合の応訴に対する相手方請求については、管理規約が定める対象ではなく、また、日本において弁護士費用等の敗訴者負担の仕組みがないことなどから、これを否定しています。
(2022.12.1)
1 事案の概要
本件は、マンション管理組合が元理事長に対し、①主位的に、総会決議(委任状無効により)が無効であると主張して、不当利得返還請求権に基づく元理事が管理組合から受領した役員報酬の返還を求め、②予備的に、総会決議が有効である場合を前提に、理事長としての善管注意義務違反に基づく損害賠償として、役員報酬相当額の損害賠償を求めるとともに、①工事の際の事務所名目で本件マンションの自己所有の居室を原告に対して賃貸したことは自己取引に当たり無効であり、理事長としての善管注意義務違反にも当たると主張して、選択的に、不当利得返還請求又は債務不履行に基づく損害賠償請求をし、②管理組合に不必要な工事をさせたことが理事長としての善管注意義務違反に当たると主張して、その損害賠償請求をし、管理会社に対し、①主位的に、総会決議が無効であると主張して、管理会社が管理組合から受領した事務管理業務費及び管理手数料の返還を求め、②予備的に、総会決議が有効である場合を前提に、債務不履行に基づく損害賠償請求として、事務管理業務費及び管理手数料相当額を求めるとともに、管理委託契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求として不必要な工事費用相当額の賠償を求めた事案。
2 裁判所の判断
(1)総会決議の有効性について
管理規約では受任者は同居者と定めているところ、委任状は同居者に限定せず組合員としていることから、当該委任状をもとにした総会決議は無効であるとの主張に対し、合理的解釈をすれば、代理人は、マンションの運営に利害関係を有する他の組合員か、当該以外の者である場合には当該組合員と同居する者に限定するという趣旨の規定であると解するのが相当であるとして、同居人以外の組合員を受任者とした委任状は有効であり、総会決議は有効であるとした。
(2)元理事の善管注意義務違反について
各修繕工事の必要性を個別に判断し、その必要性を認め、元理事に善管注意義務違反はないとした。
(3)元理事の不当利得について
元理事が自分の部屋を管理組合に貸し出した点については、自己取引に当たり、理事会の同意もなく、総会でも承認が否決されたことから不当利得に当たるとして、賃料相当額の返還請求を認めた。
(4)管理会社の責任について
管理会社の責任は否定した。
3 コメント
元理事の行為に対して、債務不履行や不法行為に基づく損害賠償請求がなされる場合がありますが、管理組合に生じた損害については、各区分所有者ではなく管理組合が原告となって訴訟を提起することになります。
(2022.11.27)